お役立ちコラム
安全運転管理者は本当に必要ない?制度概要や効果的な活用法まで徹底解説

自動車を使用する企業において、安全運転管理者の選任は必要ないのではないかと考える担当者も多いのではないでしょうか。安全運転管理者の選任は、事故を防止して従業員の安全を守るために、道路交通法施行規則にて規定されています。安全運転管理者を設置する企業は、従業員の安全を守り、企業としての社会的責任を果たすために、適切に管理者を選任することが欠かせません。 本記事では、一定台数以上の自動車を使用する企業の担当者に向けて、効果的に安全運転管理者を選任するために、選任の必要性や基準、注意点などを詳しく解説します。
- 目次
-
- 1. 安全運転管理者は必要ない?制度の概要と必要性について解説
- 1-1. 安全運転管理者制度の概要
- 1-1-1. 安全運転管理者の要件と欠格事由
- 1-1-2. 安全運転管理者の業務内容
- 1-1-3. 安全運転管理者の選任義務
- 1-2. 安全運転管理者を選任する必要性
- 2. 安全運転管理者が必要ないケースとは?
- 2-1. 使用する自動車が5台未満
- 2-2. 緑ナンバーの車両を保有する事業所
- 2-3. その他のケース
- 3. 安全運転管理者を選任する事業者が行うべきこと
- 3-1. 安全運転管理者の選任
- 3-2. 選任後の警察署への届け出
- 3-3. 法定講習の受講
- 4. 安全運転管理者の選任を判断する流れ
- 4-1. 道路交通法に基づく必須条件を確認
- 4-2. 必須条件を満たしていない場合も任意に選任できる
- 5. 安全運転管理者がいない時のアルコールチェック方法
- 5-1. 安全運転管理者がいない場合のアルコールチェック者
- 5-2. アルコールチェックの方法
- 6. 安全運転管理者を置かないことによるリスク
- 6-1. 罰則と行政処分の対象になる
- 6-2. 社会的信用の低下
- 6-3. 従業員の安全性への影響
- 7. 安全運転管理者の選任にかかる主な費用の内訳
- 7-1. 事務経費
- 7-2. 人件費
- 7-3. 外部委託料
- 8. 効果的に安全運転管理者制度の導入を進めるための4つのポイント
- 8-1. 社内の安全意識を高める
- 8-2. ICTツールを活用する
- 8-3. 専門知識や経験を有する外部企業に委託する
- 8-4. 安全運転管理者を解任する場合は慎重な判断が必要
- 9. まとめ
安全運転管理者は必要ない?制度の概要と必要性について解説

自動車事故によるリスクを軽減して従業員の安全を守るために、一定台数以上の自動車を使用する企業に対して安全運転管理者の配置が義務化されています。
ここでは、安全運転管理者制度の概要や必要性について解説します。
安全運転管理者制度の概要
安全運転管理者制度とは、一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者に対して、安全運転管理者の選任を義務付けている制度のことです。安全運転管理者は、自動車の使用の本拠となる事業所ごとに置かれ、自動車の安全な運転に必要な業務を行います。
具体的には、ドライバーへの教育や指導、運行計画の作成、車両の点検整備、事故発生時の対応などが挙げられます。安全運転管理者が、自動車の安全運行を目的とした総合的な業務を担うことで、事業者における安全意識の向上を図ることが可能です。
安全運転管理者の要件と欠格事由
安全運転管理者には、一定の要件があります。適切に選任するために、以下の要件と欠格事由を押さえておきましょう。
<要件>
| 安全運転管理者 | 副安全運転管理者 |
|---|---|
| 20歳以上 (副安全運転管理者が置かれる場合は30歳以上) | 20歳以上 |
| 自動車の運転の管理に関し2年以上の実務の経験がある/ 公安委員会の認定を受けている | 自動車の運転の管理に関し1年以上の実務の経験がある/ 公安委員会の認定を受けている/ 運転経験3年以上 |
なお、副安全運転管理者とは、安全運転管理者を補助する役割を担う存在のことです。後述する安全運転管理者と同様の業務を行います。使用台数が20台を超える場合、副安全運転管理者を選任しなければなりません。
また、上記の要件に該当していても、以下の欠格事項に該当する場合は、安全運転管理者や副安全運転管理者として選任できません。
<欠格事項>
・過去2年以内に都道府県公安委員会による安全運転管理者等の解任命令を受けた者
・次の違反行為をして2年経過していない者
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転、無免許運転、救護義務違反、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為及び要求・依頼して同乗する行為、無免許運転に関し自動車等を提供する行為及び要求・依頼して同乗する行為、自動車の使用制限命令違反
・次の違反を下命・容認してから2年経過していない
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許運転、大型自動車等の無資格運転、最高速度違反、積載制限違反運転、放置駐車違反
出典:警視庁(安全運転管理者制度の概要)
安全運転管理者の業務内容
安全運転管理者の主な業務内容は以下の通りです。
<安全運転管理者等の業務>
・運転者の状況把握
・安全運転確保のための運行計画の作成
・長距離、夜間運転時の交代要員の配置
・異常気象時等の安全確保の措置
・点呼等による過労、病気その他正常な運転をすることができないおそれの有無の確認と必要な指示
・運転者の酒気帯びの有無の確認(目視等で確認する他、アルコール検知器を用いた確認を実施)
・酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存、アルコール検知器の常時有効保持
・運転日誌の備え付けと記録
・運転者に対する安全運転指導
出典:警視庁(安全運転管理者制度の概要)
安全運転管理者の選任は、事業として自動車を使用する際の交通事故防止を目的としています。従業員の安全を守ることはもちろん、企業としての社会的責任を全うするためにも、適切に安全運転管理者を選任することが重要です。
安全運転管理者の選任義務
一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者は、自動車を使用する本拠ごとに、安全運転管理者を選任しなければなりません。
安全運転管理者の選任基準は、保有台数によって異なります。
<安全運転管理者の選任基準>
・乗車定員が11人以上の自動車:1台以上
・その他の自動車:5台以上
なお、保有台数が多い事業所では、安全運転管理者に加えて副安全運転管理者も選任する必要があります。
安全運転管理者を選任する必要性
安全運転管理者を適切に選任するためには、必要性を認識しておくことが重要です。
<安全運転管理者を選任すべき理由>
・法令や社内規則の遵守
・従業員の安全意識の向上
・事故防止
・コスト削減と業務効率化
・企業イメージの向上
安全運転管理者の要件や業務内容、選任基準は、道路交通法施工規則によって定められています。企業は、法定されている基準を遵守して、社内規則に即して適切に選任しなければなりません。
また、社内に安全運転管理者を配置することで、従業員の安全意識向上につながり、ひいては事故防止の効果が期待できます。交通事故や違反による違反金や保険料、修理費用の支払いなどのコスト削減にもつながるでしょう。さらに、効率的に安全な社内環境を構築することが可能となり、業務効率化にも寄与します。企業にとって持続可能な発展につながり、企業に対する信頼を高めることが可能です。
安全運転管理者が必要ないケースとは?

一定台数の自動車を使用する企業には安全運転管理者の配置が義務化されていますが、必要ないケースもあります。
自社のケースにおいて必要かどうかを適切に判断するために、ここでは安全運転管理者が必要ないケースについて解説します。
使用する自動車が5台未満
各事業者において使用する自動車が5台未満の場合は、安全運転管理者を設置する必要はありません。リース車両やレンタカーの場合においても、業務として使用している場合は同様にカウントします。
ただし、業務に使用している場合でも、事業者がその自動車の所有権や賃借権を有しておらず、従業員が自由に運行できる状況にある場合は、対象車両に数えません。
また、元々5台以上の自動車を保有していたものの、使用台数が減って5台未満になった場合は、届出用紙を所轄の警察署に提出して安全運転管理者を解任できます。
注意が必要なのが、台数を数える際、事業所ごとにカウントするという点です。例えば、本店が5台以上、支店が5台未満の自動車を使用している場合は、本店のみに配置義務が発生します。
緑ナンバーの車両を保有する事業所
緑ナンバーの車両とは、運送業許可を得ている、あるいは運送業に使用する営業用自動車のことです。緑ナンバーの車両については、車両数に応じて運行管理者の設置が義務付けられています。運行管理者が配置されている事業所で白ナンバーの自動車を5台以上使用している場合(あるいは、乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している場合)、安全運転管理者の選任は必要ありません。
その他のケース
安全運転管理者の選任が必要ないとされているその他のケースについて紹介します。
<その他のケース>
・業務に使用しない通勤用マイカー
・農耕用のトラクターやフォークリフトなどナンバーの付いていない特殊車両
・法人の敷地内専用の車両
従業員がマイカーとして通勤だけに使用している場合は、事業者の責任範囲外となるため、選任義務は発生しません。役員の私用車のように業務に直接使用されない自動車についても、同様です。
その他、ナンバーがついていない車両や社内のみで使用する車両においても、安全運転管理者の選任は必要ありません。
安全運転管理者を選任する事業者が行うべきこと

安全運転管理者を適切に選任するために、事前に準備しておくことがあります。適任者の選任だけでなく、選任後の円滑な運用を目指すために、事業者として行うべきことをあらかじめリスト化しておくと良いでしょう。
ここでは、事業者が安全運転管理者を選任する際に行うべきことを解説します。
安全運転管理者の選任
選任義務のある事業者は、冒頭で記載した資格要件に該当し、かつ違反行為のない安全運転管理者を選任します。自動車の使用台数が20台以上の場合は、副安全運転管理者も選任しなければなりません。
自社のケースに応じて、年齢や運転管理の経験などの要件を満たしているかどうかを調査して適切に選任することが重要です。
選任後の警察署への届け出
安全運転管理者を選任したら、届け出の手続きをします。選任した日から15日以内に、自動車を使用する本拠地を管轄する警察署を経由し、都道府県公安委員会へ届け出を提出しましょう。なお、管理者の交代や届出内容の変更時にも、届け出の提出が必要です。
<届出方法の種類>
・管轄する警察署の交通課窓口へ直接提出
・管轄する警察署の交通課へ郵送
・オンラインにて申請
届出方法には、3種類あります。郵送の場合、一部地域では受け付けていない場合もあるため、事前に確認が必要です。
安全運転管理者の選任に関する届出書類には、選任届出書や住民票、運転免許証の表面および裏面の写し、運転記録証明書、運転管理経歴証明書が必要であることが一般的です。事前に必要書類や手続きの流れについて調べておきましょう。
法定講習の受講
企業が行うべきことは、単に安全運転管理者の選任だけではありません。法定講習の目的は、安全運転管理者や副安全運転管理者が、安全運転に関する技能や最新の法令情報などの知識を継続的に習得することです。安全運転管理者などに年1回の法定講習を受講させることが、自動車の使用者の義務として、道路交通法で規定されています。
なお、最近では、オンラインにて受講できる地域が増えています。該当地域の場合は、自社の状況などに応じて受講方法を選択することをおすすめします。
法定講習の日程や受講手数料は、都道府県によって異なります。詳しいことは、各都道府県の警察本部や講習を主催する団体のホームページなどで確認しましょう。
安全運転管理者の選任を判断する流れ

ここまで安全運転管理者制度の概要や選任基準などについて解説してきました。必ずしも、全ての企業において管理者の選任が必要となるわけではありません。選任が必要ないとしても、企業として安全対策を講じる責任があります。
ここでは、円滑に社内の安全対策を講じていくために、安全運転管理者の選任を判断する際の具体的な流れについて解説します。
道路交通法に基づく必須条件を確認
まずは、道路交通法に基づく安全運転管理者の資格要件をきちんと確認して、必須要件を満たすかどうか判断することが重要です。
事業所が安全運転管理者の選任義務を満たしているかどうかは、最寄りの警察署や各都道府県の警察本部Webサイトページにて確認できます。
必須条件を満たしていない場合も任意に選任できる
必須条件を満たしていない事業所でも、自主的に安全運転管理者を選任できます。そもそも安全運転管理者制度は、事業者による自主的な安全運転の取り組みを促進する制度です。前述した通り、法令遵守や企業イメージの向上といった観点からも、企業が積極的に安全運転管理者を選任する必要性があります。
必須条件を満たしていない企業は、主に以下の点を押さえて適切に安全運転管理者を選任することを推奨します。
<任意選任の主な判断基準>
・自動車の使用頻度や運行距離、運転手の勤務時間
・過去の交通事故歴
・従業員の安全意識
・経営状況
必須条件を満たしていない場合は、安全運転対策の必要性とコスト面などにおける自社の状況から総合的に判断することが大切です。
自社の安全運転対策に悩んだら
安全運転管理者がいない時のアルコールチェック方法

2022年4月の道路交通法施工規則の改正では、安全運転管理者の業務内容が変更となりました。飲酒運転の防止を目的として、安全運転管理者による目視と運転前後における運転者の酒気帯び有無の確認、記録の保存が義務化されたことが大きな特徴です。
法改正の影響を受けて、企業としては安全運転管理者がいない場合のアルコールチェック体制についても構築しておく必要があります。
安全運転管理者がいない場合のアルコールチェック者
安全運転管理者が不在の場合、以下の人がアルコールチェックを実施します。
<安全運転管理者の不在時にアルコールチェックをする人>
・副安全運転管理者
・安全運転管理者の業務を補助する役割を担う人で事前に会社内で指定された人
副安全運転管理者が不在の場合は、運行担当者や管理職など、会社内で指定された人が対応します。運行担当者や管理職などが対応することが一般的です。
その他、アルコールチェック代行サービスを導入する方法もあります。自社の状況やコストとの兼ね合いを考慮して、検討しましょう。
アルコールチェックの方法
アルコールチェックに関して、道路交通法施工規則では2022年4月と2023年12月の2回にわたって改正されました。2023年の改正により、目視確認とアルコール検知器を用いた運転手の酒気帯び有無の確認とその記録の保存、アルコール検知器を常時有効に保持することが義務化されています。
従来、アルコールチェックはバスやタクシー、トラックなどの緑ナンバーを使用する企業のみが義務化の対象とされていましたが、2022年の法改正により以下の企業も義務化されました。
・白ナンバー車両で乗車定員が11人以上の自動車を1台以上所有
・白ナンバー車両の自動車を5台以上所有(自動二輪車は1台を自動車0.5台として計算)
※所有台数は事業所単位で計算
なお、運転手が直行直帰する場合は、自らアルコール検知器を使用してチェックし、安全運転管理者に結果を報告する必要があります。
安全運転管理者を置かないことによるリスク
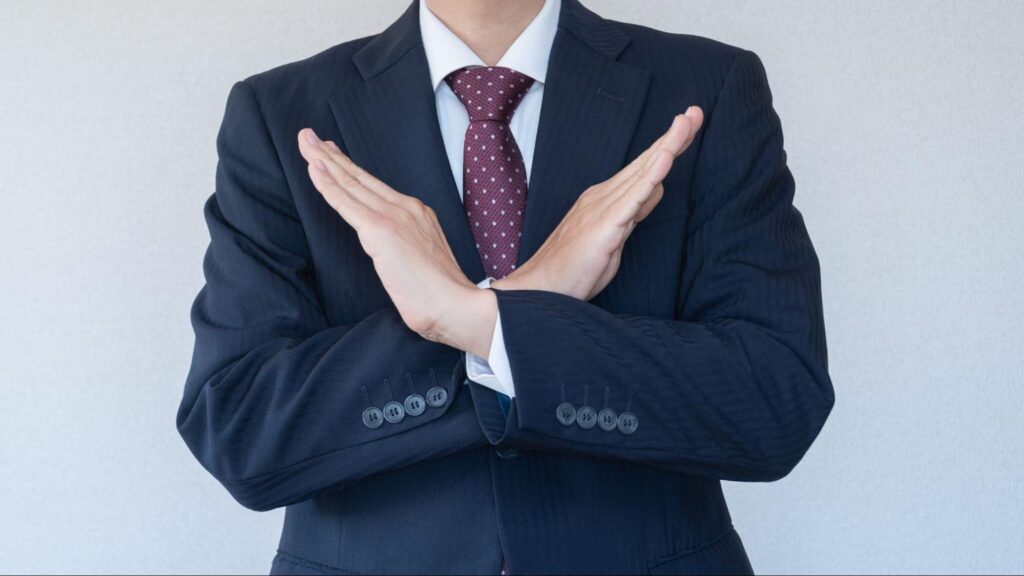
安全運転管理者の設置が必要であるにもかかわらず、選任しない場合には罰則や行政処分の対象となります。
ここでは、安全運転管理者を設置しない場合のリスクについて解説します。企業にとってリスクがあるからということではなく、事故防止と社会的責任を全うするという目的のために、法令を遵守して適切に対応することが重要です。
罰則と行政処分の対象になる
安全運転管理者の選任義務があるにもかかわらず、選任しなかった場合、道路交通法に基づき50万円以下の罰金が科されます。
その他、安全運転管理者制度に関する違反行為に対する罰則には以下があります。
<安全運転管理者制度に関する主な罰則>
・選任解任届出義務違反:5万円以下の罰金
・解任命令違反:50万円以下の罰金
・是正措置命令違反:50万円以下の罰金
なお、悪質な違反が続く場合は、行政指導や業務停止命令がくだされることもあります。道路交通法の改正に伴い、違反行為に対して大幅に厳罰化されました。選任や解任時の届出を提出する場合、また解任命令や是正措置命令を受けた際は、適切かつ迅速な対応が求められます。
社会的信用の低下
安全運転管理者制度に関する違反行為は、道路交通法違反となり、企業の社会的信用の低下を招くおそれがあります。
取引先や顧客からの信頼低下につながり、企業のブランドイメージを損ないかねません。取引停止のリスクが高まり、機会損失を招く可能性があります。さらに、こうした企業イメージの低下は、従業員のモチベーションダウンにもつながるでしょう。
法的な罰則だけでなく、企業イメージの低下といったリスクを避けるためにも、適切に対応することが重要です。
従業員の安全性への影響
安全運転管理者を設置しないことで、管理不備による事故につながる可能性が高まり、従業員の安全が脅かされるおそれがあります。
また、安全運転管理者を置かずに事故が発生した場合、企業責任を問われることになります。損害賠償を受けるようなことがあれば、企業の存続に影響を与えかねません。
さらに、必要な安全管理を怠った結果、違反や事故が多発することで自動車の保険料率が上昇する可能性もあります。
従業員の安全という安全運転管理者制度の根本的な目的を理解した上で、法令に従い適切に選任することが大切です。
安全運転管理者の選任にかかる主な費用の内訳

安全運転管理者を設置して運用するためには、コストがかかります。また、安全運転管理者の他にも、企業が安全運転対策を講じるためにはさまざまな費用が発生することを押さえておきましょう。
安全運転対策にかかる費用は、事務経費と人件費、外部委託料に分けられます。ここでは、それぞれの項目について解説します。
事務経費
安全運転管理者を選任する際、選任届出書の作成が必要となり、事務経費がかかります。他にも、安全運転マニュアルや安全教育資料、安全運転管理規定などの作成費用や印刷費などの費用が挙げられます。
また、書類を郵送する場合の郵送料や事務用品などの費用が発生することも押さえておきましょう。
ただし、作成する書類の量や郵送する頻度などによって、費用が変わります。予算の範囲内で運用していくために、具体的に発生する事務経費について確認しておきましょう。
人件費
人件費も考慮しておくことが重要です。選任後、安全運転に関する知識の習得に必要な講習を管理者に受講させる際にも手数料がかかります。
安全運転管理者を設置する際にかかる人件費は以下の通りです。事業規模や管理者の経験などによって、費用は異なります。
<安全運転管理者に対して発生する主な費用>
・安全運転管理者講習の受講料:5,100円(副安全運転管理者3,400円)
・給与
・資格取得費用
・研修費
安全運転管理者以外にも、企業の安全運転対策を担う存在が、安全教育担当者や安全パトロール担当者です。安全教育担当者に対しては、給与や研修費用といった費用がかかります。また、安全パトロール担当者については、主に交通費や給与といった費用が必要です。
担当者の人数や給与水準によって費用は変動することから、予算に合わせた運用が欠かせません。
外部委託料
自動車の安全運転対策を外部に委託する場合は、外部委託料が発生します。
外部委託料には以下が挙げられます。
<主な外部委託料>
・安全運転診断費用:事業所の安全運転体制に関して診断してもらうための費用
・安全運転教育研修費用:外部講師による安全運転教育についての研修費用
・安全運転コンサルティング費用:専門家に安全運転に関するコンサルタントを依頼する費用
・設備導入費用:ドライブレコーダーや車載カメラなどの設備導入にかかる費用
・安全運転車両の購入費用:安全運転機能を搭載した車両の購入費用
外部委託料は、委託機関の規模や依頼内容によって異なります。突発的な費用が発生する可能性も考慮して、余裕を持って予算を組むことが大切です。
効果的に安全運転管理者制度の導入を進めるための4つのポイント

安全運転管理者制度の導入には、企業に対する信頼向上といった効果があります。ただし、効果的に進めるためには、いくつかポイントを押さえておくことが大切です。
ここでは、効果的に制度を導入するために必要な4つのポイントについて解説します。
社内の安全意識を高める
安全運転管理者制度を導入したとしても、社内ではたらく従業員の安全意識が低ければ適切に運用できません。社内の安全意識を高めるためには、社内教育を定期的に実施していくことが必要です。
社内教育の内容は、安全運転の厳守や安全運転の心構え、事故防止対策などが一般的です。講義だけでなく、ロールプレイングや実習を取り入れることで従業員の理解が深まります。
また、経営層が、社内の安全運転意識向上についての取り組みに対して積極的に関与していくことも重要です。
安全運転意識向上のための取り組みには以下が挙げられます。
<安全運転意識向上のための主な取り組み>
・安全運転のスローガンを作成する
・安全運転優良者を表彰する
・安全運転についてのコンテストを実施する
社内教育や安全運転意識向上のための取り組みを実施しても、短期的に成果が出るとは限りません。長期的な視点に立ち、継続的に取り組んでいくことが大切です。
ICTツールを活用する
安全運転管理に関するICTツールの導入で、業務の効率化を図ることができます。具体的には、ドライブレコーダーやGPS運行管理システム、安全運転指導システムが挙げられます。
ドライブレコーダーを搭載することで、運転状況を記録して事故発生時の状況を把握できます。同時に、危険運転を検知して、運転手の傾向を分析した上で、従業員に合う適切な安全運転教育を実施することが可能です。
GPS運行管理システムとは、GPS機能により車両の位置情報を正確かつリアルタイムに把握できるものです。過労運転や速度超過といった危険運転につながるおそれがある場合に、適切な指導を実施して事故の防止につなげられます。
また、eラーニングなどオンラインによる講習を受けられるように安全運転指導システムを導入することも効果的です。
コストと自社の課題を考慮して、安全運転管理を円滑に進められるICTツールを活用しましょう。
TTS株式会社では、通信型ドライブレコーダーでの映像とGPSによる安全運転管理が可能です。映像とGPSデータを統合して管理することで、事故リスクを減らすことができ、企業の安全運転教育にも活用できます。動態管理システムに関する詳しい内容については、TTS株式会社までお問い合わせ下さい。
専門知識や経験を有する外部企業に委託する
安全運転管理を自社だけで進めていくとなると、コスト面や担当者の業務量などの観点から多くの負担がかかります。負担を軽減して効果的に安全運転管理者制度を導入するためには、外部企業に業務を委託することを推奨します。
<外部企業に委託できる主な業務内容>
・安全運転管理体制の構築・運用
・事故原因分析
・事故再発防止策の策定
・安全運転データの分析
・安全運転講習の実施
安全運転管理体制の構築と運用には、管理規定の作成や安全運転教育の実施、安全運転指導員の選任などが該当します。また、事故が起きた場合の原因分析と再発防止策の策定といった業務内容も、外部企業に委託することで専門的な分析結果を得られるでしょう。
また、外部企業に委託してドライブレコーダーや運転日報などから日頃の運転状況を分析する作業も、安全運転管理に不可欠です。こうした業務を外部に委託することで、効率的に指導や運行管理を進められます。
さらに、外部講師を招いて安全運転教育を実施することで、社内の負担を軽減しつつ専門的な指導を展開できます。
安全運転管理者を解任する場合は慎重な判断が必要
安全運転管理者を一度選任した場合でも、選任基準を満たさなくなった場合はもちろん、職務怠慢や違反行為、不正行為などの一定の事由に該当する場合は解任できる可能性があります。
ただし、安全運転管理者を解任すると、社内の安全運転管理体制に影響を与えかねません。管理者の解任を検討する場合は、解任後の社内の管理体制を想定した上で総合的に判断することが重要です。
なお、安全運転管理者を解任する際は、解任した日から15日以内に届け出を提出する必要があります。
届け出の提出方法は、以下の通りです。
<解任の届け出の方法>
・事業所の所在地を管轄する警察署の交通課窓口に直接持参
・事業所を管轄する警察署の交通課宛に郵送
・警察行政手続サイトにてオンラインによる届け出
まとめ

本記事では、安全運転管理者制度の概要や必要性、注意点などを解説しました。安全運転管理者の選任は、事故を防止し安全性を高めることを目的としており、道路交通法施行規則では一定台数以上の自動車を使用する使用者に対して義務付けています。企業が安全運転管理者の選任義務を果たすことは、法令を遵守し、社会的責任を全うするために必要なことです。
ただし、自社だけで社内の安全運転管理を進めることは容易ではありません。外部企業のサポートを受けて、コストを考慮した上で効率的に進めていきましょう。
TTS株式会社では、車両の現在位置や移動履歴、稼働状況をリアルタイムに把握できる車両動態管理システムを提供しています。
<主なラインナップ>
- 通信型ドライブレコーダー(AI解析対応モデル):リアルタイム映像と位置情報の統合管理が可能なタイプ
以下の機能が備わっています。
・ADAS機能:前方衝突・急接近・車線逸脱などをAI検知し警告
・DMS機能:わき見、居眠り、スマホ操作などのドライバー異常を検出
- OBD型/シガーソケット型デバイス(工事不要モデル):車両の電源ポートに差すだけで設置完了(配線・工事不要)
以下の特長があります。
・リアルタイムのGPS位置管理が可能
・急ブレーキ・急カーブなどの挙動を加速度センサーで自動検知
・運転日報や移動履歴の自動生成に対応
TTSソリューションの導入により、社用車に関するリスクから従業員の安全を守ることができます。ぜひTTS株式会社までお問い合せ下さい。
車両管理の基礎知識に関する記事
-

2025.12.03
車両管理の基礎知識
コンテナの追跡とは?海上輸送中のコンテナの位置を把握する方法を解説
輸入や輸出を日常的に行う貿易事業者や製造業・商社などでは、海上輸送中のコンテナの位置を把握したいというケースも多いでしょう。海上輸送中のコンテナは追跡(トラッキング)が可能です。コンテナの位置を正確に把握することは、顧客対応の質向上や業務の効率化において非常に重要です。 本記事では、コンテナの追跡方法とコンテナを追跡することの効果について解説します。
-

2025.10.29
車両管理の基礎知識
本船動静をリアルタイムで追跡する方法は?船舶輸送を可視化するメリットを解説
国際物流に携わる企業にとって、貨物船の位置や到着予定を正確に把握することは大きな課題です。 出荷から納品までの流れを円滑に進めるためには、サプライチェーン全体の可視化と効率的なリスク管理が欠かせません。近年はデジタル技術の発展により、船舶の動静をリアルタイムで追跡する手段が拡大しています。 本記事では、リアルタイム追跡が求められる背景や確認方法、GPSトラッカーを導入する際のポイントまで詳しく解説します。
コスト削減・業務効率化に関する記事
-

2025.12.03
コスト削減・業務効率化
配送ルート最適化で何が変わる?データ活用で進む物流DXの効果
物流現場では、ドライバー不足や燃料費の高騰、短納期化など多くの課題が重なり、従来の経験や勘に頼ったルート設計では限界が見え始めています。配送効率を高めながらコストや労務負担を抑えるためには、データに基づく配送ルート最適化の考え方が欠かせません。 本記事では、荷主企業の物流担当者や生産管理担当者、商社の調達担当者などに向けて、配送ルート最適化の仕組みや背景、導入による効果、具体的な実践方法をお伝えします。AIやクラウドを活用した仕組みを理解することで、業務の再現性と生産性を高められます。
-

2025.10.29
コスト削減・業務効率化
運転日報の保存期間とは?法的基準から効率的な管理法、システム導入まで徹底解説
運送業や旅客業、または一定以上の営業車を保有している企業などは、運転日報の作成が法律で義務付けられています。さらに、作成するだけでなく、一定期間保存する必要があります。運転日報の作成や保存を怠ると、最悪の場合罰則につながるため法的な要件について正しく理解することが重要です。 この記事では、運転日報の保存期間や運用のポイントについて解説します。運転日報の業務への活かし方や電子化によるメリットについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
-

2025.10.29
コスト削減・業務効率化
安全運転管理者は本当に必要ない?制度概要や効果的な活用法まで徹底解説
自動車を使用する企業において、安全運転管理者の選任は必要ないのではないかと考える担当者も多いのではないでしょうか。安全運転管理者の選任は、事故を防止して従業員の安全を守るために、道路交通法施行規則にて規定されています。安全運転管理者を設置する企業は、従業員の安全を守り、企業としての社会的責任を果たすために、適切に管理者を選任することが欠かせません。 本記事では、一定台数以上の自動車を使用する企業の担当者に向けて、効果的に安全運転管理者を選任するために、選任の必要性や基準、注意点などを詳しく解説します。
防犯・紛失対策に関する記事
-

2025.12.03
防犯・紛失対策
建設現場での重機盗難を防ぐ!物理ロック・カメラ・GPS追跡まで徹底解説
建設・土木の現場では、重機が盗まれれば即座に損失と工期遅延につながります。特に油圧ショベルなどの中小型重機は、短時間でも搬出されやすく、夜間や無人時間帯はリスクが高まります。 本記事では、重機を所有・運用する土木・建設会社や重機レンタル会社の担当者・経営者に向け、現場で本当に役立つ盗難対策の全体像を整理します。盗難防止では、「物理的な防犯」「監視」「検知・追跡」の3段構えが重要であり、各対策を組み合わせて多層的に備えることが被害を防ぐ鍵となります。
-

2025.10.29
防犯・紛失対策
【トレーラー盗難防止の最新対策まとめ】物理ロック×GPS追跡まで徹底解説
結論として、トレーラー盗難の実務対策は複合的に進めることが重要です。「物理ロックの多層化」「保管環境の整備」「ICTによる検知・追跡」を同時に実装することで、防犯性は段違いに高まります。 盗難が発生すると稼働が止まり、配車計画の乱れが工期や納期へ波及しかねません。代替トレーラーの手配や再配車で費用や膨らみ、事務負担も増えるリスクがあります。 本記事では、トレーラー盗難の被害の傾向と、多発しやすい環境を確認しましょう。併せて、効果的な物理的なロックとICT・IoTを活用した盗難対策についても解説します。












